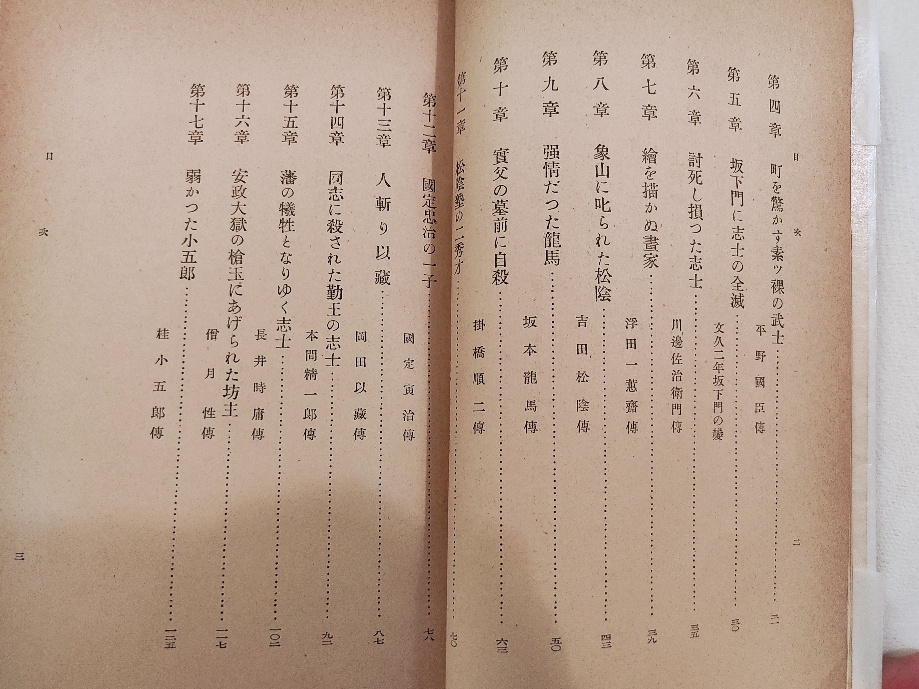塚越鈴彦の伝記である。またの名を塚越酸素彦とも名乗った。酸素!? 変った名前だ。実は訓みは同じ「すずひこ」。
小浜藩士で明治3年アメリカに渡った人である。明治6年に帰国。横浜税関の吏員となりその生涯を終えた。明治19年、42歳の若さであった。明治初年に渡米経験をした人物にしてはあるいは活躍の場に恵まれなかったといえるかもしれない。伝記がなければ今日その存在を知る人はほぼいなかったであったろう。
著者はこの人の次男。父親が亡くなった時はわずか4歳であった。著者にとって亡父の伝記を編むことは、おぼろげな記憶にしか残っていない父親の姿を蘇らせ再会するための行為であったろう。
伝記の冒頭に以下の文章がある。
余は四の時、父を喪ふた。其の際姉てるは拾貮歳、兄卯太郎は八歳であつた。余尤も幼くして父の風貌を知るに由なかった。 稍長ずるに及び、母は色々父の物語を吾々に聞かせた。余は又十三四歳の頃より毎夏、母より曝書の手傳を命ぜられたが、それは凡て父の愛讀書、遺稿及び交友との間に往復せる書簡等であった。
此の曝書の手傳をすることは少年たる余に取り何等苦痛ではなく、寧ろ楽しみであった。 余は之の古き文書に接する毎に感興の無限に湧き来るを禁じ得なかったからである。斯様にして余は母の物語と文書研究とに依り、幾分でも父の風格を知ろうと力めた。
中略
澤山ある書類の中で最も重要な資料となったのは「金蘭簿」である。之は父が渡米前後の生活を簡単に記したノートで父の経歴を知るには欠く可からざる資料である。
中略
爾来今少し材料を集め、尚ほ母の物語などを参照して、父の経歴、性行等に関し聊か綴った記述を試みたいとの念が常に脳裡から去らなかったが、種々の事情のため、荏苒二十有餘年、到頭今日に及んだ。偶ま今次、小閑を得て書簡其他の書類を殆ど全部参照して「金蘭簿」を根幹として此書を編述したのである。依て之を「金蘭簿物語」と題した。
塚越鈴彦は小浜藩士であったが、実は武家の出でも小浜出身でもなかった。上州新田郡太田(群馬県太田市)の人ではじめは良之助といった。太田の塚越家といえば新田義貞にゆかりの一族で、義貞が越後で敗死すると新田荘反町館に残っていた義貞の妻子を匿って由良に逃した塚越氏が知られている。(その塚越氏の支族にあたるのだろう)太田宿近くの金山に住んだ塚越家のさらに分家の次男に生まれている。
文久元年、学問好きが高じて江戸に出て昌平黌へ入学。
しかし実家本家の家産が傾くと学資が途絶えてしまい、やむなく退校。
その後は医家の玄関番をした。伊東玄朴の世話になったこともあるという。
面白いのは、山岡鉄舟の門下となり新徴組にも加わっていたともいうのだ。伝記にはそのあたりのことがさらりと書かれているだけなので、残念ながら具体的な事歴として確定することはできない。しかし、伊東玄朴との交流に関しては塚越の妻シゲの詳言(『幕末明治女百話』)があるので確かだったことが分かる。伝記の叙述も細部にはそれなりの根拠があることなのかもしれない。新徴組の入隊に関しても何かしらの証明が見つかるといいのだが…。
新徴組には太田宿近郊の東上州からは多くの人物がその前身の文久3年の上洛浪士組以来参加している。人脈的にはあり得る話だ。
もっとも新徴組に加わっていたとしてのごく短期間だったようで、その後は、年次は不明ながら(伝記では慶応元年と推定)山岡の紹介で神奈川奉行所付属の「下番」(外国人居留地の警護員)になっている。鐵の橋(吉田橋)関門の警備隊に配属された。当時の隊長は多田元吉。多田とはこの時以来の縁で後に鈴彦が亡くなるとその墓誌銘を多田が草している。ちなみに多田といえば旧幕臣から勧業寮の役人になり製茶産業を興し本邦紅茶の祖として伝記(川口国昭『茶業開化 明治発展史と多田元吉』全貌社、1989年)も編まれている大物。前に投稿した内国勧業博覧会の大久保利通を中心とする集合写真にも大久保の近くにいる。https://oldbook.hatenablog.com/entry/2022/06/07/161648
さて、神奈川奉行所の下番といえば、新選組に加入前の篠原泰之進や服部武雄、加納鷲雄、佐野七五三之助らといった人物たちがいたことで知られている。時期的にかぶっていたかは微妙な線ではあるが、彼らが鈴彦と同僚だったことがあったとしたら面白い。
鈴彦は下番としての勤務の余暇に外国人に英語を学ぶようになる。よほど上達したのだろう、横浜に藩の英語教師を探しに来ていた小浜藩士池田正吉の目にとまり、その推挙で江戸藩邸での英語訓導に従事することになった。慶応3年9月、26歳の時に五人扶持を供され小浜藩士となった。
横浜時代、鈴彦は英学・医学・化学分野に特に力が入っていたようで、それまで良之助と名乗っていた名前を酸素彦(すずひこ)に改めている。化学へ強い興味からだろう。後にはその奇なる名前を鈴彦という穏当な漢字に直している。
この横浜時代に星亨と知り合っている。「横浜に来て、鐵の橋関所の隊中に勤務する旁、英語研究に従事し、太田町の長家で、自炊生活をして居た。丁度、其長家の一軒置いて隣に居を定めたのが、星一家で、其為め偶然、父は星と相知るに至った」
星亨は鈴彦から英学を学んだ。
「学問にかけては、余の父の方が、先輩格であったことは勿論で、後年に至っても、星の母は、余の父に対して、常に先生々々と言って尊敬していた、といふに徴しても、単なる友達関係では無かったのである」
鈴彦は小浜藩に召し抱えられるにあたり、星亨を助手として伴った。牛込矢来町の江戸藩邸に二人は同居して自炊生活をおくった。「一人が豆腐屋に走れば、一人が八百屋に行く、といふ様な具合で、極めて親密に日を送ったのである」
江戸藩邸で藩士に約一年間英学を教えると、今度は若狭の藩地に転住することになった。そこでも鈴彦は星を小浜に伴っている。しかし肝心の藩地では鈴彦らの兵術を含まなかった純英語学には藩士子弟たちは興味が薄かったようで、担当講座はまるきり人気がなく生徒が集まらなかった。二人は早々にモチベーションを失ってしまう。星亨は小浜を去って大阪へ向かった。一方、鈴彦は米国への自主渡航を計画することになる。小浜藩籍のままに渡航費の一部を藩費から出してもらい、足りない分は現地でなんとかするという願書が受け入れられ明治3年6月にチャイナ号に乗って米国に渡った。
米国では特定の教育機関にじっくり留学する形式をとらず、ほぼ行き当たりばったりのようなサヴァイヴをしたらしい。丸善の洋書輸入の代理業をしたり、日本語教授の新聞広告を出してアメリカ人に教えてギャラを得たという。最終的には森有礼代理公使の時の日本公使館の書記官の職を得ている。しかし残念ながら運悪く病によって欠勤がちになり結局短期間で解雇されてしまう。明治6年に帰国。
この経歴から想像するに非常にバイタリティー豊かでかつコミュニケーション力が高く面白い性格の人物だったと思われる。
「外にあっては社交上、頗る面白く、時々滑稽洒脱の言葉が口を出ると言ふ按排」だった。鈴彦の妻シゲはたびたび人に「塚越さんは随分面白い方ですね」と言われたという。しかし妻にはこの他人の夫のへ印象が全く理解できなかった。実は、鈴彦は外面と全く違って家庭生活においては窮屈単調で無味乾燥、家庭では全然しゃべらない。あまりに会話もしない夫に堪忍袋の緒が切れた妻が「何か面白い事でも話してくださいませ」と頼んでも「ウンわしは毎日、日本人許でなく、西洋人、支那人などと色々話ばかりしているからもう沢山だ」と答えて取り合わなかったという。しかも負け惜しみが強く頑固だった。当時の日本人男性は多かれ少なかれ同じような傾向だったであろうが、現代ではまず定年後に熟年離婚を切り出されされるタイプの男性像の人だ。
著者は亡き父親に対して思慕の念ゆえに伝記を書いたわりには、母の話ではたいして慈父というわけではなかったのだ。読み手のこちらは勝手に感動的な物語を作ってしまう訳で、この梯子外しはある意味痛快で楽しい。
ちなみに鈴彦の妻シゲ(明治7年に結婚)は長命して、あの篠田廣造の百話ものに80代になって貴重な談話を残している。
『明治開化奇談』(明正堂、昭和18年)「幕末明治の世態推移」
『幕末明治女百話 前編』(四條書房、昭和7年)「怪傑星亨の阿母さん」
『幕末明治女百話 後編』(四條書房、昭和7年)「お大名大奥の着附と年中行事」
の三編でシゲの語りを読むことができる。篠田は当時80歳のシゲに関して「元気旺溢、記憶精確」「刀自の快話に包まれた著者は幕末の世界に逆転し」「獲難き實話」を取材したと述べている。
シゲはある種の女傑で夫の死後女手一つで3人の子供育て上げた。長女は山一證券の創業者小池国三に嫁いでいる。息子二人も実業界で活躍した。
『幕末明治女百話』で語っているが、シゲは星亨のあのクセ強の個性的な母親と上手く付き合えたらしい。凄いことだ。
『金蘭簿物語』の口絵写真には鈴彦が明治15年に横浜税関所員らと一緒に撮った写真が掲載されている。官員録でみると15年当時の横浜税関員には彰義隊士で箱館戦争にも参加し後に横浜毎日新聞に記者となった丸毛利恒の名前を見つけることができる。鈴彦の部下であったわけだ。この写真はキャプションが鈴彦以外の人物になく他の税関員の人物比定ができなくて大変残念なのだがおそらくこの中に丸毛も写っていると思われる。

武士姿の塚越鈴彦の写真は、『塚原夢舟翁』(大正14年)に載っている。鈴彦が中心で右に星亨、左に塚原夢舟がいる。この写真は慶応4年に星亨が小浜藩に採用されるときに江戸で撮ったものという。

鈴彦は谷中に葬られた。谷中霊園に鈴彦の墓が現存しているのかどうか私は確認できていない。
墓はもう一箇所、故郷の太田市金山の受楽寺の塚越家の墓域にもある。そちらは展墓したことがある。父親と兄の墓の脇に甥によって建碑された。小さな木が生えていて名前を隠している。